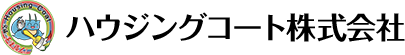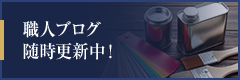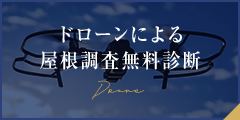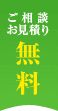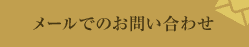福岡市早良区高取のS様から「外壁に虫の巣みたいなものが付いているので見てほしい」とご連絡をいただき、調査に伺いました。
虫の巣というと珍しいように感じるかもしれませんが、外壁では案外よく起こる症状です。巣ができるということは、虫にとって都合の良い条件が外壁に生まれているということで、その意味でも一度確認しておく価値があります。
![]() 「ここなんですが、土の塊みたいなのがくっついてるんです」
「ここなんですが、土の塊みたいなのがくっついてるんです」![]() 「これは泥蜂の巣の跡ですね。外壁の小さな凹みや塗膜の弱りを好んで作るんですよ」
「これは泥蜂の巣の跡ですね。外壁の小さな凹みや塗膜の弱りを好んで作るんですよ」![]() 「やっぱり虫の巣だったんですね」
「やっぱり虫の巣だったんですね」![]() 「はい。見た限り最近できたもののようです」
「はい。見た限り最近できたもののようです」
現場ではこうした巣をよく見かけますし、毎回“たしかにここなら作るよな”と納得する部分にできていることが多いんです。外壁は風や光の影響を受けて少しずつ変化していきますが、その変化を虫は敏感に察知しているように感じます。
![]() 「これ、放っておくと良くないですか?」
「これ、放っておくと良くないですか?」![]() 「跡の部分から水が入りやすくなる場合がありますね」
「跡の部分から水が入りやすくなる場合がありますね」
巣そのものは小さくても、跡が外壁の弱点になることがあるため、気づいた時点での調査はとても意味があります。
外壁に虫の巣が作られる理由を確認
![]() 「なんでここに作ったんでしょう?」
「なんでここに作ったんでしょう?」![]() 「虫は柔らかかったり乾いていたりする場所を選びます。特に紫外線で塗膜が弱ると表面が少し粗くなって、巣を固定しやすくなるんです」
「虫は柔らかかったり乾いていたりする場所を選びます。特に紫外線で塗膜が弱ると表面が少し粗くなって、巣を固定しやすくなるんです」![]() 「そうなんですね」
「そうなんですね」![]() 「さらに、日当たりや風の流れも影響します。その家の環境によって、虫が寄りつきやすい場所が決まることが多いですよ」
「さらに、日当たりや風の流れも影響します。その家の環境によって、虫が寄りつきやすい場所が決まることが多いですよ」
外壁を見ていると、巣ができる場所には必ず理由があると感じます。小さな凹み、乾燥した部分、少し影になる位置、風が抜ける向きなど、いくつかの条件が重なる場所に集中する傾向があります。長く調査をしていると、巣を見るだけでその家の外壁のクセが分かる瞬間があります。
![]() 「同じ高さにいくつかありますね」
「同じ高さにいくつかありますね」![]() 「どれも条件が似ていますから、同じ時期に作られた可能性が高いですね」
「どれも条件が似ていますから、同じ時期に作られた可能性が高いですね」
巣の並び方は風の抜け方や日差しの強さをそのまま表しているようで、外壁って本当に環境を映す鏡だなと感じます。
外壁の状態を触診しながら確認
![]() 「このあたり、指で触るとザラつきがありますね」
「このあたり、指で触るとザラつきがありますね」![]() 「たしかにそうですね」
「たしかにそうですね」![]() 「紫外線の影響で塗膜が弱ってくると、こうした質感になります。虫が巣を作りやすくなるのもそのためなんです」
「紫外線の影響で塗膜が弱ってくると、こうした質感になります。虫が巣を作りやすくなるのもそのためなんです」
外壁は見た目がきれいでも、触ってみると劣化が進んでいることがあります。経験上、ザラつきや粉っぽさが出た部分は、雨水を吸いやすくなることが多く、そのサインが巣として表面に出ることがあります。
![]() 「こちら側は少し湿気が残りやすいですね。汚れが付きやすいのもその影響です」
「こちら側は少し湿気が残りやすいですね。汚れが付きやすいのもその影響です」![]() 「なるほど」
「なるほど」![]() 「湿気の影響を受ける場所と日差しに焼ける場所では劣化の進み方が全く違います。虫もそのわずかな違いをうまく使っているようです」
「湿気の影響を受ける場所と日差しに焼ける場所では劣化の進み方が全く違います。虫もそのわずかな違いをうまく使っているようです」
調査をしていると、一つの巣をきっかけに外壁全体のバランスが見えてきます。表面の変化は小さくても、家の外側ではいろいろな力が働いていることを改めて実感します。
外壁に虫の巣を見つけたときの考え方
外壁に虫の巣が付いている場合、その周辺では塗膜の弱りや小さな凹みが起きている可能性があります。巣を無理に剥がすと塗膜がいっしょに取れてしまい、そこから雨水が染み込むこともあります。外壁は一度傷むと連鎖的に劣化が広がることがあり、小さな跡でも油断できません。
虫の巣は、外壁が今どんな状態なのかを知らせてくれるサインと言えます。巣そのものよりも、巣が作られた理由に目を向けることが大切で、その理由が分かると外壁の弱点がどこなのかがはっきり見えてきます。塗膜の質感、周囲の湿気、日差しの当たり方、汚れの付き方など、いくつもの条件が絡み合って外壁の表情を変えていきます。
外壁は毎日天候にさらされ続ける場所なので、小さな変化が積み重なって大きな差になります。虫の巣を見つけたときは、異変を教えてくれたと思って一度状態を確認することが外壁を長持ちさせる第一歩になります。
太宰府市・筑紫野市・小郡市・大野城市・福岡市東区・福岡市早良区で、
外壁の虫の巣や気になる付着物を見つけた際は、まずは調査からお気軽にご相談ください。
外壁の状態に合った適切な対策をご説明いたします。